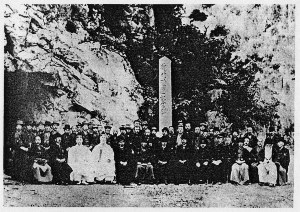| 龍 | 化 | 隧 | | | 行政:兵庫県川辺郡猪名川町 | 標高:140m |
| 道 | ■ | ■ | | | 1/25000地形図:妙見山(京都及大阪11号‐1) | 調査:2005年8月 |
|
■背景 Background
V字形に二股に分かれた一庫ダム.水没二隧道はいずれもその左の又にあって,上流側に当たるのが龍化隧道である.一庫ダムの平常満水位(145m)よりわずかに下にあるため,洪水対策として水位が下げられる6月〜9月の4カ月間だけ姿を現す.
■調査 Experiment
渇水期の国道173号を走ると,普段はダムの湖面下にある谷の深さ,蛇行の激しさに改めて驚かされる.大阪の平野からここまで登ってくれば,そしてさらに上流に広がる豊能・能勢ののどかな山里風景を知っていれば尚更だ.地質の具合なのだろうか,ちょうどここら一帯だけが峡谷のようになっていて,交通の難所であっただろうことは容易に想像がつく.
このうねる谷を満喫するには,やはり現国道より湖岸の道路を通るほうがいい.大阪側からアプローチするなら,一庫ダムまで登って右折(県道野間出野一庫線)し,ダム堰堤から左に折れれば湖面沿いの道に入ることができる.龍化隧道に会いに行くだけなら,もう少し国道を進んで,新円山トンネルの手前で右に折れたほうが早い.
ダムに沈んだ集落の一つ,国崎集落は,この碑から北東方向に伸びる谷にあった.林業と一庫炭と呼ばれた炭焼きが主な産業であったという.北東の谷と北西の大路次川とが出会う辺り,ちょうどダムの最底部には,出合という集落があり出合橋があった.ちなみにダム湖東岸の谷の一つにはかつての集落の産土神であったろう神社が残っている.石の鳥居や壊れかけた石灯篭などもあったように記憶しているが,今はどうなっているだろうか. ダム堰堤に端を発する道は,通称さくら橋(知明1号橋・ランガー桁)でV字の中央に渡る.龍化隧道へはここで左折である.ここで右折すると無料の駐車場があり,車を置いて付近を散策したい方にお勧めしたい.但し夕方5時くらいで閉まってしまうはずなので注意されたし. 
右に左に何度も揺さぶられつつ,断崖の道を北上する.左手下方には知明湖の緑色を見下ろす.意外に森も深くてそう悪くない雰囲気の道である.今回の調査のメインディッシュたる円山隧道が先に見えてくるが,写真は後のお楽しみに取っておこう. 
龍化隧道もこの対岸の道から見下ろすことができる.真正面を向いた大きな素掘り隧道はなかなかの迫力である.坑口を見ると天井のわずか上まで泥をかぶっているのがわかる.平常水位ではぴったり隠れてしまうのだ. 大路次川の右岸に渡れば,足元の川べりへ下る階段がいくつもある.隧道のある付近もまた遊歩道として整備されているようである.但しそこへ至るためには,もう100mほど北に進んで,遊歩道用の吊橋を渡らなければならない. 
龍化隧道の北側坑口.でかい.高さは5m近くあるだろうか(右端の自転車に注).調査時には天井にスズメバチの巣があったのだが,それがあまりにも離れて見えて,存在が気にならなかった程の高さである.幅もそれなりにあって,さすがはかつての国道隧道,といった貫禄がある.素堀り隧道でこれだけの幅・高さがあるのは珍しいかも知れぬ.
隧道内は下流側に軽く傾斜している.両脇には排水用の溝とコンクリート蓋も見える.竣工は大正時代だが,意外と改修を受けているようである.抜けてすぐ道が右に折れているため,隧道内からは対岸の崖しか見えない.この道は下流にあった円山隧道へと向かっていく(ただし現在ある道は遊歩道用に整備されたもので,直接円山隧道につながるものではない).
南側坑口の向かって右手には石組+コンクリートの土台あり.これは竣工直後に記念碑が建てられた場所のようである.左写真が竣工当時の龍化隧道,右がほぼ同じ角度で南側坑口を写したもの.左写真の人の列の背後にあるオベリスクが開通記念碑である.この位置と人の高さ,写真左端に見えている隧道坑口の高さを見比べてみると,当時よりも拡高されていることがわかる(写真は報告者が持参した資料を見つめる絹路氏). 最後に,円山隧道を調査し終えた一行が南側坑口付近でカレーを作っている図.これはnoa氏が撮影した一枚也.まさかこの隧道も,こんな怪しげな一行が訪れようとは思ってもいなかっただろう.
■考察 Discussion 現在は猪名川町の町域にある龍化隧道だが,開鑿にはより上流の能勢町の出身人物が関与している.開通記念碑は彼のことや隧道開鑿のいきさつを刻むだけでなく,大路次川に沿って作られていた明治の道───これも地元の人々が作り,後に兵庫県に寄付されて丹州街道と命名された───の歴史も教えてくれる.丁度良いのでこの碑文を引用することで考察に代えたい.
「龍化隧道記念碑 藤沢南岳書 巨巌渓を圧し,渓又激して竜化の瀑となる.畳み掛けるような韻が何とも言えない.如何にも明治大正の知識人といった感が滲み出していて,報告者は好きだ.
■参考文献 References
|

| ||

|