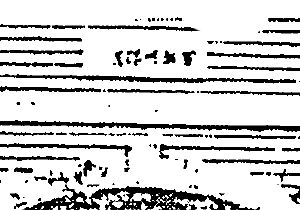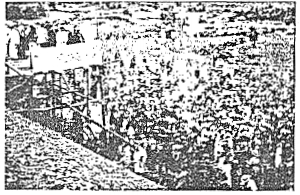|
■考察 Discussion
百瀬川隧道は,ポータル前に設けられたゲートの存在からもわかるように,今日の道からすればややアンダースペックとなってしまっている.より直截的に云えば邪魔者だ.前後の道は2車線幅なのに内部が1.5車線しかないせいで,自動車は自然,交互通行とならざる得ない.報告者が調べている間にも車が立ち止まり,対向車をやり過ごしては抜けていく姿を何度も見た.そもそも百瀬川という天井川も厄介者である.ひとたび大雨が降れば決壊する危険性が高く,周囲の民家は常に怯えて生活しなければならない.
百瀬川の北約100mのところに,生来川という川が雁行している.居住区の手前で百瀬川をこの川に導き,それより下流を枯れ川にする計画だ.2005年の時点では,隧道より下流側,国道161号の百瀬川大橋の手前で生来川に接続する仮工事が完了している.工事はさらに上流へ向かい,やがて百瀬川隧道も取り壊される運命にある.
こういう時,地元の人間でもない報告者がどういう態度をとるべきか.非常に悩む.本来土木とは,そこに住む人々の生活を幸せにするために行われるもの.たとえ近代化遺産として価値があったとしても,人々が望まないなら取り壊されてしまっても仕方がないのかも知れぬ.アーチ環についた数多くのひっかき傷も無言の圧力のように思えてならない. 湖西地方の土木事業を司るのは,滋賀県湖西地域振興局である.ここに隧道のことを問い合わせたところ,「百瀬川の沿革誌」という冊子があることを伺った.これは内部の人物が内部で閲覧することを目的として作られたものであったため, 公文書公開の手続きを踏まねばならないことになり,数々の手間をおかけした結果,半月後にようやく写しを入手することができた. どうしてどうして,内覧だけで終わらせるには勿体ない内容である.百瀬川を生み出す原因となった地質のことから旧百瀬村の字名の変遷,江戸時代から何度も繰り返されてきた治水工事の歴史まで,古文書の写しも交えながらの詳細な解説である.さながら郷土史研究書のようだ.肝心の百瀬川隧道はあまり詳しく書かれていないものの,当時の姿を知ることのできる写真が2枚載せられていた.
お世辞にも鮮明とは言えない写真だが,ここから貴重な情報を3つ,読み取ることができる.1つは隧道ポータルの中央部にも下見板風の装飾が施されていること.完成当初はやはり全面が下見板張りであったことがこの写真から確認できた.
もう一枚の写真も完工式典の模様を写したものだが,不鮮明なために何を写したものなのかはっきりしない.左手の土手らしき所に櫓があって多くの人が立ち,またその下にも数え切れないほどの人々が集っている.恐らく隧道の前に詰めかけた人々を,百瀬川の土手から俯瞰気味に撮ったものと思えるが,それにしてもすごい人だかりだ.櫓も特別観覧席か何かのような感じがする.これほどまでに,人々を歓喜させた隧道だったのかと改めて驚くばかりである. 本文には次のように記されてある。
「 村内唯一つの随道(注;原文ママ.以下同)で何故に随道形状になったのか、理由は西近江路の路線上(大字沢地先)に百瀬川が流下しており、この河川は天井川で古来から屡、堤防決かいを繰り返し道路交通上の難所でもあった。 少し補足すると,「西近江路」は同誌別ページに仮定県道西近江路とあり,旧百瀬村の中心部を通って沢,蛭口から右折して海津から敦賀に向かうものであった,「仮定」は県道に準じるものという意味で,県道として整備する候補道路みたようなものであり明治〜大正までの名称である.大正9年の旧道路法公布により今津敦賀線と改められ,隧道建設もこれに合わせて行なわれたものだろう.大津と敦賀を結ぶ路として国道161号に指定されるのは,太平洋戦争後,1953年(昭和28年)のことである. 同じ下見板張り風の装飾を持ちながら,ピラスターに個性的な違いがあった鈴鹿隧道と百瀬川隧道.百瀬川隧道の4本ピラスターはそれまで県内に作られた隧道からの流れであることは確かだ(鈴鹿隧道は坑口両脇の2本だけ).そして完成時期からすれば鈴鹿が先であって,百瀬川隧道はその装飾をまねて下見板を採用したと考えることができる.また鈴鹿隧道が2年で完成しているところからすると,はるかに規模の小さい百瀬川隧道は1年もかからなかっただろう.それからすると,完成した鈴鹿隧道を見てヒントを得,百瀬川隧道の意匠を設計したと考えても無理ではない.そこで敢えてピラスターの装飾を違えたのは,単なる真似に終わらせないぞという,設計者の心意気の現れと言えそうだ.
■参考文献 References
|

| ||
| ||

|



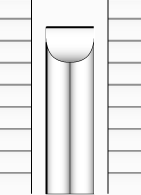 もう1つはピラスターの模様.鈴鹿隧道のピラスター中央に刻まれた凹模様は,十字を縦に長く伸ばしたような単純なものであった.鈴鹿隧道と同じ三鉾状の頂石を持つ隧道も,ほとんどがこの十字型をも継承している.一方,百瀬川隧道のそれは,全く別の形だったようだ.建築用語をよく知らぬ報告者なので何と表現したらいいのか解らぬが,四角い枠の中に円柱を2つ並べて埋め込み,さらにその凹部上端も半円形の装飾がなされているようで,立体的に表現すると右図のようになると思われる.このような装飾のピラスターは他の隧道でも見たことがない.
もう1つはピラスターの模様.鈴鹿隧道のピラスター中央に刻まれた凹模様は,十字を縦に長く伸ばしたような単純なものであった.鈴鹿隧道と同じ三鉾状の頂石を持つ隧道も,ほとんどがこの十字型をも継承している.一方,百瀬川隧道のそれは,全く別の形だったようだ.建築用語をよく知らぬ報告者なので何と表現したらいいのか解らぬが,四角い枠の中に円柱を2つ並べて埋め込み,さらにその凹部上端も半円形の装飾がなされているようで,立体的に表現すると右図のようになると思われる.このような装飾のピラスターは他の隧道でも見たことがない.