 録"
録"
nagajisの日不定記。
本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0
ad
2011-01-08 [長年日記]
[資] 明治10年三重県:県道以上道路掃除及小破修繕受負規則
○地乙第三号 十年一月十八日達 <一志以南緒郡志摩一円牟婁半郡>
区戸長
夫道路は掃除の忽略より歩行の困難運輸の不利を起し為に意外の破壊を生じ随て修繕の費用も増加するに至る因て別紙県道以上に属すべき見込の分規則の通り本年より施行候条各区限り諸路の距離を実測し受負人住所身分姓名年齢并村界標柱の員数代価及実測人夫賃等に至る迄悉皆取調一区に纏め二月三十日迄に可申出此旨相達候事
但熊野街道<山田より牟婁に至るもの>等の如き其線路の内谿谷山腹等に係り掃除せしむるも徒に費用を消費するのみにて其益なきか或は他道と雖も定例二度の掃除一度にて足と見認るものは実測の際区戸長に於て見込相立箇所限り別段取調伺出べし県道以上道路掃除及小破修繕受負規則
- 第一条
- 凡県道以上に属する道路は其行程距離を実測し受持場を区分し一村毎に受負人を置<受負人の都合により一人にて幾村を受負うも又一村を幾人にて受負うも妨げなしと雖も他区に越え跨るを得ず>小破の修繕及掃除をなさしむるべし
但市街及村落人家前の如きは各自の受持たるべし- 第二条
- 凡掃除及小破修繕の町場は一区を限界となし尋常の箇所は二百十円[注:間の誤り?]険難及人家遠隔の場所は<初瀬街道の内青山峠和歌山街道の内高見峠の如き類を言う>百二十間を以一人一日に修掃するものとす
- 第三条
- 道路掃除の限界を確定し紛乱ならかしめん為村界毎に区限りの番号を付したる標柱を建設すべし
但標柱書式は第一図を見合すべし- 第四条
- 凡受負人の給料は其掃除一度毎に尋常道路は二百十間険難及人家遠隔の箇所は百二十間に付金二十銭の割を以て支給す尚受負人の便宜に依り事故の対談を以人夫を雇入掃除せしむるも妨げなし給料受取方は該区吏員に於て三ヶ月毎に仕訳書を製し一区限り取纏め翌月十日限り県庁へ申出べし
但第二仕様書書式を見合べし- 第五条
- 小破<水溜り車掘れ等を言う>修繕の如きは掃除の内に属する手数なれば別に賃銭を給せず尚是に属する用器の如きも其掃除人にて相弁せしむべし
- 第六条
- 凡掃除の度数は一ヶ月二度とし毎月<五日二十日>を以其掃除着手の定日とし若し降雨なれば順次日送に着手し掃除済の上該<区村>区戸長に届出べし其余定限度数の外臨時に掃除を要する時は区戸長より其事故を県庁に具状し許可を得べし或は県庁より掃除を達するも亦其事故を詳記して之を区戸長に達すべし
但臨時に属する給料も第四条の手続を以請取方申出べし- 第七条
- 請負人掃除の精粗勤怠を監督するは其請持村戸長は勿論区長に於ても篤く注意し戸長に於ては掃除済の時日を見計巡視致し疎略の箇所あらば再び掃除を命じ後に再び巡視すべし県庁に於ても主務官員をして臨時派出監査せしめ且各区巡査に於ても粗略の所業を見認るときは其村戸長に照会督達する事あるべし
但本条の如巡視し不都合なしと見留たる上は仕訳書を造り見届人之に検印して入費請取方申出べし若之を怠り仕訳書に検印なきものを出すときは入費下渡さず尤県庁より巡回検査に至り[鹿+ク]漏あるが如きに至りては仮令入費下渡たる後と雖も其費用を引揚ることあるべしこの場合に至ては其見届人に帰すべし- 第八条
- 暴風雨雪等の節は往来の妨害を慮り請負人に於て其請持の町場を見回り破損の箇所及倒木類あらば該区戸長に届出指揮を請くべし
- 第九条
- 臨時修築其他事故あって掃除をなさざる節は其時々県庁に届出べし
- 第十条
- 右掃除に係る費用は管内割民費より仕払ものとす
第一図の内宅地有之村の例
用材楢木
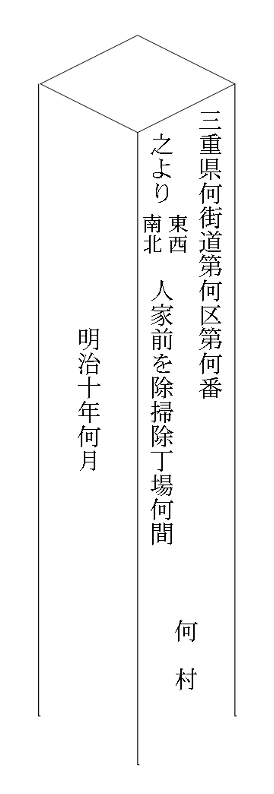
(注:右図入る)
方面三寸地上より高二尺五寸根入二尺
同宅地無之村町の例
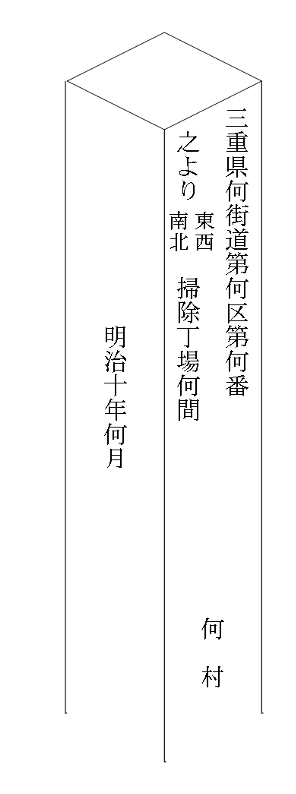
(注:右図入る)
右同断
道路名称は九年地甲第五十六号に照準すべし
第二仕様書々式 (朱円の処見届人検印すべし)
何街道々路掃除費○<何月より何月迄>仕訳書
一金何程 道路掃除請負給料
是は第何区何番町場長何間分但一ヶ月二度づつ都合何度一度<二百十間百二十間>に付金二十銭づつ
(一人にして幾村も受負うものあれば本行是は書を除き左の如く内訳すべし)
内 訳
金何程
是は何街道第何区第何番云々前に同じ金何程
是は右同断前書之通常例(或は臨時何々に付<臨時は条例と混せず別紙に仕訳書を製すべし>)掃除致度候処相違無之に付書面之給料御下渡被下度候也
第何区何村
道路掃除受負人明治何年何月 何の誰 印
区戸長連印
長官宛
(街道及受負人毎に各通に認べし)(別紙)
県道以上道路掃除費概算
- 国道第二等
- 伊勢街道 一志郡小森上野村より度会郡宇治迄
- 行程八里二十九丁二十一間三尺
- 県道第一等
- 和歌山街道 飯高郡松坂より大和国高見峠国界迄
- 行程十五里三十二丁五十五間二尺七寸
- 同 第三等
- 初瀬街道 一志郡三渡村より青山峠伊勢国界迄
- 行程七里六町四十八間一尺八寸
- 同
- 熊野街道 度会郡山田より牟婁郡新宮界迄
- 行程四十里二丁四十二間
- 同
- 鳥羽街道 度会郡山田より鳥羽迄
- 行程三里三十四丁二十六間三尺
- 同
- 奈良街道 一志郡中林村より安濃郡五百野村界迄
- 行程四里四丁五十四間四寸
- 同
- 和歌山別街道 多気郡野中村より粥見村迄
- 行程五里十九丁二間一尺二寸
- 総計八十五里二十二丁二十間一寸
- 右の内凡三分通人家前となし間敷を除く
残十二万九千四百五十八間
但一人二百十間を以一日に掃除する者とし一ヶ月二度づつ一度の給料金二十銭則一ヶ年分(<険難の箇所は実測の上に無之ては難分に付算せず>)
金二千九百五十九円三銭二厘
外臨時掃除一ヶ月一度づつと予算し
金千四百七十円五十一銭六厘
二口
合金四千四百三十八円五十四銭八厘 <一志以南諸郡志摩一円牟婁半郡>此金額の如きは概略の算出なるが故実測したる上は必ず増減あるべし
金三千百六円十八銭八厘 <安濃以北諸郡伊賀一円>
総計
金七千五百四十四円七十三銭六厘[出典:三重県令達全書 原文カナ旧漢:<>割注]
明治9年地甲第56号は道路調製規則。里道の路線調査を市町村に命じるもの(後に国県道になることになる路線が示され、それを除く里道相当の道を調査するよう命じるもの)。ここでは国県道だと明示されているわけではないが、街道名としてこれを用いよということらしい。
[資] 明治9年10月18日 天甲第五十九号 国道県道及人家稠密の地へ看板日覆ふらふ竿及牛馬繋杭等の義略則仮定
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788789/27
12年甲第91号により廃止。「公九、後上 七十三丁」は公文全誌へのポインタで、この本が存在しない。
[資] 明治9年11月4日 地甲第五十八号
等級制度から国県里道制度への過渡期を示す達は見つかった。道路調製概則の達の直後だ。
○地甲第五十八号 九年十一月四日達
区戸長
今般河港道路等級被廃候に付ては堤防修繕願并入費金高帳等是迄何等何川通と記載せしを更に何川<即幹川>流域何川<即支流川>と箇所毎肩書に記載可致道路之義は分類等級追て確定可相成に付夫迄の内は道路橋梁修繕同断金高帳等の義箇所毎肩書に某地より某地に達する某街道<即東京より京都府に達する東海道と記すの類>と記載可致候此旨相達候事
但工事及費用の義は先づ従前の通可相心得候事
[出典:三重県令達全書 原文旧カナ、<>割注]
追って分類等級を示すので、それまでは路線経由地を書いてしのげ、ということ。かといってこの後に分類等級が示されたかというと……そうでもない。次に出てくるのは道路掃除小破受負規則。
[資][独言] 現状:目論見:まとめ
何度か書いたが未だにうまくまとめられずにいる。しつこく書いてみる。
明治6年大蔵省達番外・河港道路修築規則によって道路が一等・二等・三等に分類されるようになった。その後明治9年太政官達60号で国県里道制へ移行。このとき国県道は国が指定することになっていて、地方に対して道路調書を提出するよう命じた。しかし数が膨大になったことや、提出できなかった府県(県?)もあって、指定はダダ遅れに。そのうえ明治14年[要確認]から土木費下げ渡し制度が廃止、地方税によって賄われることになった。
結果、国道は明治18年になってやっと国道表ができ、県道は各府県が仮に認定して当座を凌ぐことになった。このあいまいな処置は大正8年に(旧)道路法が制定されるまで続いた。
以上、日本道路史や日本土木史から得たあいまいな知識。
知りたいこと
(旧)道路法以前の県道の扱い、および位置付け。例えばいつ(どのタイミングで)県道が指定されたのか。国道は明治18年に定まったというが、それ以前から県道が存在した県がある。明治9年の国県里道制度を受けてすぐさま指定があったのか、それとも二等道路を引き継いだのか。
仮定県道という言葉の生まれたいきさつ。いきさつというかいつ頃生まれたものなのか。管見では国が「仮定」県道として指定せよと達するようなことはなかったように見受けられる。そもそも県道指定を県に委ねる達も見ない。どこかにあるのか、それともないのか。
解決のためのアプローチ
当時の県の法令を読む。三重県は比較的古い達・県令訓令告示をネットで見ることができる。端々当たっていけば何かわかるかも知れない。なお三重県は「三重県史」編纂中で通史編は出ていない。資料編近代はある。
三重県だけだと偏るので、近畿2府4県も目を通す。
現状認識
三重県の場合、明治9年太政官達の直後から県道に関する具体的な措置が取られている。例えば国県道に不要物を設置することを禁じたり(明治9年天甲第59号)、県道以上の道路に掃除者を置く制度を設けたり(明治10年地乙第3号)。特に後者達では県道一等和歌山街道、三等熊野街道などが明示的に記されている(何故か国道まで書かれてある)。但し県道路線を指定する達は出されていず、それは三重県史資料編近代にも収録されていない。おそらく旧三重県・度会県時代に何らかの形で一等道路・二等道路が定められていて、それが明治9年太政官達を受けて自動的に国県道になったものと思われる(それをわざわざ告示はしなかった)。そもそも明治6大蔵省番外達も明治9太政官達も(国が示すつもりだったため)路線指定を公示することを義務付けていないのだから、当然といえば当然かも知れない。なおこの頃の三重県令では「仮定」を冠していない。
土木費下げ渡しが廃止された頃から道路の扱いがやや変わってくる。国県里道の区分とは別に「その道路の土木費の扱い」で区分した区分。三重県の場合は一等道路、二等道路といい、一等道路は国・県・主要里道で(基本的に)全額県費支弁、二等道路はそれ以外の里道で、一定割合をもって補助するとした。県や県民にとってはその区分のほうが大事であったためか、県道○○街道というよりも一等道路○○・二等道路△△のように呼ばれることが多かったようだ(これに似た制度は近畿各府県でも見られ、明治19〜21年にかけて制定されている。奈良県は明治26・27年にその議論がある)。
関係するかどうかは未だ不明だが、この頃から「仮定」県道という言葉が目につくようになる。三重県では明治15年(だったか明治13年だったか)から達のなかで「仮称県道」が使われる。統計書では明治19年版から一等二等の区分とともに国道・仮定県道・里道が併記される(それまでは単に街道という括りで、かつ、後の里道に相当する道は掲載されていない)。
そういうわけで、三重県では早い段階から県道が定まっていたが、法令・告示で明文化されたものではなかった。明治19年土木費支弁法でも実は明確に示していない(国県道という括りで15道が列記されているだけ)。なのに統計書では区分がされているという不思議。
他県を見るに、明示的に県道とその路線を指定する告示を出している所とそうでない所がある。
明示型:滋賀県・奈良県
非明示型:福井県・京都府・三重県・和歌山県・大阪府
未確認:兵庫県
滋賀県には三重県の一等二等のような制度はなかったように見受けられる(少なくとも明治20年代までには)。県費の支弁がある道路すなわち県道という前提のもとで?県道路線を告示している。奈良県は土木費支弁法(県令)のなかで「県道は全額支弁、主要里道は○割補助」とし、別に県道路線を告示。主要里道は土木費支弁法のなかで示してある。京都府は補助割合を指定するだけでこれといった呼び名はなく、そのうえ県道という言葉すら最後まで使わなかった。府という制度上、土木費負担は郡区が担ったからか?(その割には大阪府も似てる)
といった具合に、県道の扱いはひどくまちまちだった。各府県の土木費の取扱いも調べないといけない。大変。