 録"
録"
nagajisの日不定記。
本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0
ad
2023-05-01 [長年日記] この日を編集
[きたく] 甲大門西暗渠にて
長手に刻印らしい窪みを見つけて採刻しようと考えていたら通りがかりの人に話しかけられるという、昨日の北浜田暗渠@武豊線と同じシチュエーション。「煉瓦の刻印を見つけたのでどこのだろうと考えてたんです」とRDFを展開しつつ「ほら、これが」と照らした先に、さっきのとは違う、より鮮明な刻印があった。えっ。

うぇいおうなんでここにこれがあんねんと混乱してしまったのが運の尽きだ。話の相手をしつつ市古工場の識別印がある理由と年代の整合性を考えつつ市古工場が碧海郡いまの碧南市にあった工場で東は天竜川の辺りから西は草津駅まで使われてることを語る裏で何かを決定的に勘違していると思いつつ話し続けなければならなかった。その方が立ち去ってから違和感の根源がわかった。こいつ市古の識別印じゃねえ。「○+カナ」じゃなくて「○+かな/カナ」だ。瀬田川橋梁下で採取済みのあいつだ。湖東線で突き止められずにいるままのあれだ。甲大門西橋梁は複線分を一建立で作ってあるし、もともとM25時点ではここに煉瓦暗渠はなかったから、複線化の時に新造したとすれば瀬田川のも複線化の井筒から出てきたものということになってすべての辻褄が合うのである。複線化の時にこの付近を大掛かりに改造したことになる。乙大門西も宮東も喜内前もそうなんだ。揖斐川の東岸もそう(上江崎を除いて)。
というわけで、2023年5月1日午後4時頃甲大門西暗渠で変な人にまくしたてられた方、嘘を言ってしまった。ごめん。
RDFを張るのが下手になっている。というか喋ること自体がかも知れぬ。だから電凸をしたくなかったのだ。とにかくいろいろ下手になっている。その証拠にこの狭さだから車なんかくるめえと思って暗渠内で荷物展開して採刻していたらクラクションを鳴らされてたまげた。地元おっちゃんが軽トラックで突っ込んできたのだ。サイドミラー擦らないと抜けられないほどギリギリなのに。車にRDFが通用するとは思っていないが実際そうなってしまうとやはりなんだかなあである。ていうかやめてほしい。。。
コンビニに寄った帰りの電車出発まであと20分という時には乙大門西暗渠でも同じのを見つけ、10分以内で採刻し得た。こんなことばっかり上手くなったってなあ。
高価なものをぶっ壊して悄気げたりもしたが、北浜田暗渠がオリジナルでないらしいこととか五六川橋梁の井筒が露出しているとか市古工場の位置を絞り込めたこととかいった「情報」と「記憶」は何にも代え難い、決して失われることのない収穫なのだと思うことにして慰めている。まあそれだってnagajis惚けたら木阿弥三太郎なんだけどな。そうなる前に書き留めておかなければならない。揖斐川橋梁前後の新築暗渠が並形系列でただ一つ上江崎の北口だけ違うとか。あいつホントは堅積みなんだぜ。

あと甲大門西暗渠には鳥の足型のついた煉瓦が混じっている。
2023-05-02 あーっ!!! [長年日記] この日を編集
2023-05-03 [長年日記] この日を編集
[煉瓦刻印]うーむ

同じ採刻印でも押し方によって結構歪むことを発見。朱肉の載せ方、押し方によってこれくらいは変わり得ることは知っといたほうがいい。青のほうはちょっと傾いて押した上でぐりぐりしてしまった。もともと印自体が摩耗しているので、例えば伸ばし棒の下のほうだとか、濁点の端だとかは印の中央付近よりも「浮いて」しまう。それを転がすようにして押してしまうとちょっと変わってくる。押し方を統一するよりも比較の時にそれぞれで揃えるしかなさそうだ。
2023-05-16 [長年日記] この日を編集
[資] 西尾士族生産所 人名対応
どっかに置いとかないと自分が参照できない。
| 漢字 | ランプ小屋採刻? | 橋梁に検出? | 名簿にある? | 身分 | 名前 |
| □西 | yes | no | yes | 西尾士族 | 西村伊之松 |
| 西尾士族 | 西村久五郎 | ||||
| 西尾士族 | 西村義三郎 | ||||
| □大 | yes | no | yes | 西尾士族 | 大谷庸次郎 |
| 東端村 | 大岡道松 | ||||
| 東端村 | 大橋源吉 | ||||
| 棚尾村平民 | 大竹由三郎 | ||||
| □市 | no | no | yes | 西尾士族 | 市川嘉市 |
| 西尾士族 | 山口市蔵 | ||||
| 小川村平民 | 市川周吉 | ||||
| □長 | no | no | yes | 東端村平民 | 長田元蔵 |
| 富山村平民 | 長谷鈴三郎 | ||||
| □國 | no | no | yes | 西尾士族 | 國友利蔵 |
| □角 | no | no | yes | 北大浜村平民 | 角谷喜太郎 |
| □南 | no | no | yes? | 役員(西尾士族) | 南東 |
| 役員(西尾士族) | 南隼太 | ||||
| □木 | yes | no | yes? | 役員(西尾士族) | 木口半也 |
| □平 | yes | yes | yes | 西尾士族 | 平井吉蔵 |
| 西尾士族 | 平井鍬三郎 | ||||
| 大浜村平民 | 平松廣吉 | ||||
| □青 | yes | yes | yes | 道光寺村平民 | 青山重次郎 |
| 道光寺村平民 | 青山良吉 | ||||
| 戸ケ崎村平民 | 青山米吉 | ||||
| □萩 | no | yes | yes | 西尾士族 | 萩山安次郎 |
| □圡 | yes | yes | no | ||
| □斗 | yes | yes | no | ||
| □池 | yes | no | no | ||
| □泉 | yes | no | no | ||
| □近 | yes | no | no | ||
| □又 | yes | no | yes | 士族 | 村山又五郎 |
| □石 | yes | no | yes | 上町村平民 | 石川奥次郎 |
| 碧海郡棚尾村平民 | 石川道助 | ||||
| 左 | yes | - | - | ||
| 板 | yes | - | - |
2023-05-18 [長年日記] この日を編集
[独言]東洋組覚書
M20.5. 会計課主計係近藤義次の作成した回答案。知事→内務県治局長。2種あり、後者の方がやや詳しい。東洋組は諸工業の試験と実業を目的とした会社で発起人は斎藤ひとり。株主なし。その中に瓦製造会社と煉化製造会社がありそれぞれに定款を定めていた。株主募集はこれら会社についての株。賦金は東洋組に対してのもので、その棄捐の責任を両会社の株主に負わせられるかどうかは法律上の問題。また瓦製造・煉化製造会社は合併して天工会社となった(天工会社株主は東京華族を中心とした5?名)。ここで天工会社が倒産すると事態がさらにややこしくなるため(県の方で)懇篤説諭した結果、東京株主の朝山頼誉が地方税貸金一万六〇五〇円を弁済、愛知株主の粟生重寔が賦金五九〇〇円を弁済することで合意。また東京株主は旧西尾藩士に株を譲り、旧西尾藩士は精成社を新設して事業を継続。朝山の地方税貸金はたしかに弁済したが粟生負担の賦金が未済のまままだったようだ。以上のようないきさつから東京株主に対して賦金弁済を求めることはできないとしている。而してこの時点で「精成社も土崩瓦解するに到れり」で顛末が終わっているが、精成社はM19.3.時点で解散し西尾士族生産所になっているはずなのに書かれていない。而してM19.3.時点で鉄道省御用の煉化を製造していてM21.22.棚卸表がある。粟生負担の賦金を「食い切る」ための精成社であり廃業ならんか。
東洋組発起人は名前は出てこず「資力なきものなり」と埒外。M19.末頃に南部が代納を願い出たり取り下げたりしている間に裁判があった?(破産宣告された?)
2023-05-23 [長年日記] この日を編集
[きたく] ふう

いろいろあって心が折れそうだが、結果的には案外よく頑張っていた。よかった。
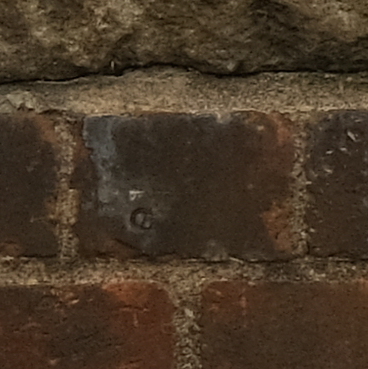 ○Dが撮れていたので黒姫駅ホームの煉瓦の構成は半場川橋梁と同じ傾向だとわかったのは収穫。採刻して比較できなくても、まあ、いいか。それが核心にはならない。
○Dが撮れていたので黒姫駅ホームの煉瓦の構成は半場川橋梁と同じ傾向だとわかったのは収穫。採刻して比較できなくても、まあ、いいか。それが核心にはならない。
2023-05-24 [長年日記] この日を編集
[独言]直江津線メモ
大田切以北はM19代に竣工。以南はM20代。坂口新田、大田切、郷田切がM21代(M19末着工)。ゆえに以南の資材を建設中の線路で運ぶことはできない。碓氷峠越えで運び込んだものがかなりある。
豊野~三才間などはM21。大田切以北と違う煉瓦なのはわかる。直江津から運び込んだものと碓氷峠越えのものと?大田切の煉瓦が高い位置にありすぎてはっきり見れなかったのが難。あの風化の仕方は大田切ゆえなのか、それとも普通なのか。多くの暗渠がC巻増しで長手を観察できなかったのもつらい。逆に表面が剥離しやすい煉瓦だったからC巻補修がされているのかも知れないが。どこかで一つだけ見たヴォールトの見れる暗渠の煉瓦確認のこと。
市古工場の煉瓦は郷田切の建設時や坂口新田の仕上げの頃(ポータルを構築している頃)に持ち込まれたか。その余りが黒姫駅に。
それらと千曲川橋梁のは同じか別か。
2023-05-29 [長年日記] この日を編集
[煉瓦] 井筒深さメモ
那波光男「軟弱なる地盤に建設せられたる橋脚橋台の構造と竣成後25年間の経過に就て」(『土木学会誌』第7巻第1号 大正10年2月発行)
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00034/07-01/07-1-11288.pdf
関西本線揖斐川橋梁。最大第4号橋脚の85.017ft、最小第15号橋脚50.41ft(笠石天端から刃口まで)。長径30ft短径15ftの楕円形井筒。
R.V.BOYLE "The Rokugo River Bridge and Foundations on the Tokio-Yokohama Railway, Japan."
12ft円形井筒を使った24, 25,26号橋脚はレール下79ftまで沈下。平均で地表下56.80feet、最大80.67feet。
『明治二十年度鉄道局年報』
https://dl.ndl.go.jp/pid/2523523/1/8
天竜川橋梁。「同川河底の地層は泥土若くは細砂にして重量に堪え難きを以て八十呎以上の深さまで沈降せざれば完全なる基礎を得ざるもの多し」「本期の末に於て煉瓦井筒の沈降平均六十一呎」
富士川橋梁。「河底より廿呎乃至四十呎にして岩石の層に達したり」。大井川橋梁も同程度。
永尾勝義「新しい瀬田川橋りょう」(『JREA』10(2)、昭和42.2.)
https://dl.ndl.go.jp/pid/3255856/1/20
新瀬田川橋梁の基礎は潜函工法で15m≒50ft沈下。