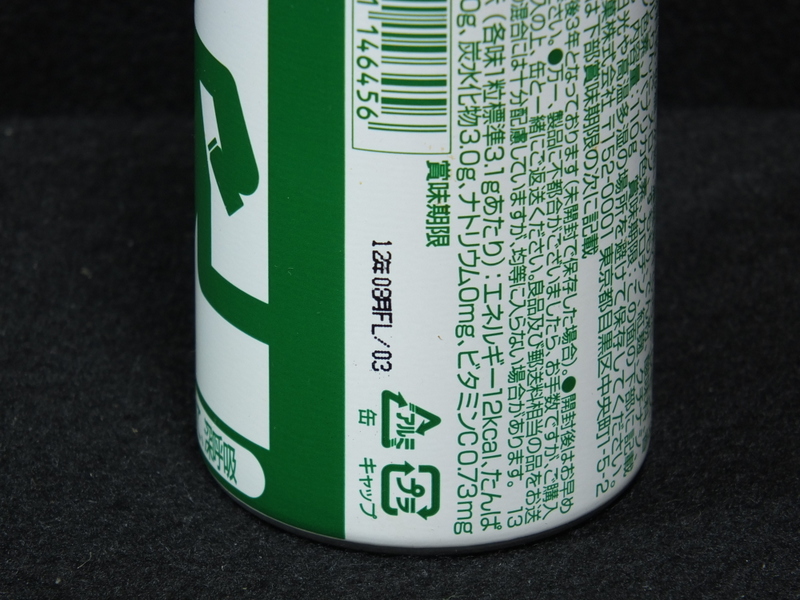録"
録"
nagajisの日不定記。
本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0
ad
2020-02-03 [長年日記]
[独言] 豆まき
夕方6時過ぎに豆を買いに行ったらどこにも置いていなかった。それどころかもうバレンタインデーとかひまなつりとかが始まっておった。そのくせ恵方巻きは定価販売という強気。大豆業界とは癒着していないのだろう。いいことである。
仕方なくコープさんでドライパックの大豆を買ってきて撒いた。すごいねこれ、茹でてあってすぐ食べられるのに乾燥してる。乾燥してるというか適度な湿度が保たれている。撒いたらホコリまみれになるかと思っていたがそんなことはなかった。
[煉瓦] 再三の長田区
「ランプ小屋」刻印を探して長田区を歩いたが……残念長田、もとい残念ながら、第二第三の刻印は発見できなかった。
出かける前の希望では、北尻池町で大正7年から製造を始めた長田煉瓦(株)が第一候補だった。この工場は明治頃から窯業を営んでいたらしく「今昔マップ」の最も古い版に窯記号が描かれている。いまの高速長田駅の南東方、セブン-イレブンの西隣の辺りだ。それでこの場所を手始めに、一番町〜五番町、新湊川の縁、そこから南へ御蔵通とか東尻池町とか苅藻町とかを歩き回った。
n番町は明治の旧版図で住宅密集地帯になっている辺りよりも、その周辺地域で煉瓦を多く見た。明治の集落中心はほとんど全面がマンション・アパートの敷地になっていて跡を留めていない。見られた煉瓦は和田煉瓦とか播煉三本線とか東山工業所の釘カナ印とか、大正・昭和初期の工場のものばかりで、街の拡がっていった時期と一致するらしく見えたのが面白かった(明治の地形図では一面耕作地。大正の版から疎らにまんべんなく民家が建つようになる)。
御蔵通は震災ですっかり焼けてしまったところ。今日ではもうすっかり復旧して、いかにも住みやすそうな、広い間隔を開けて建つ住宅街になっている。古いものなど何もない・・・と思ったけれども、その片隅に移設されたお地蔵様の祠の足元で和田煉瓦のワを見たりした。
真野・東尻池・苅藻・浜添はかなり広範囲に長屋街が残っていて、そんな長屋の路地側溝に今でも煉瓦が使われている。前回歩いたのはごく一部だったので、今回はthrough the every passesのつもりで歩き回った。特にレアな煉瓦は見つけられなかったが、前回は見なかった大正煉瓦、ちょっと珍しい関野煉瓦▲、吉名煉瓦らしい○Y、丸丹を検出。前2件は位置的にあっておかしくないものだが、そういえば前回は見なかった。

泉州の煉瓦は、やはり岸和田煉瓦が最も多い。次いで大阪窯業があり、堺・日本・貝塚が稀に出てくる。この付近は明治時代にもまばらな民家街なので、その頃持ち込まれたものが転用を重ねて現存しているのかも知れない。ともかく長田区下では播州煉瓦団が最も優勢で、そうして特にこれが多いというものがないのは興味深かった。この地域の開発にあてこんで一斉に供給したように見える(先述2工場と伊東窯業は1例ずつ。路地ごとあるいは建物ごとで刻印が違うカンジ)。
p>

ちょっと面白かった例。旭硝子の初期の製品と思われる237mm四方の四角い耐火煉瓦である。19.9という数字、R−109?という記号が書かれている。社章以外はおそらく手書き。
それで結局川崎車両工場まで行ってしまったのだけれど、会社に凸するのは諦めた。最近ちょっと気弱モードなのでうまく立ち回れない気がしてね。たぶん電話で聞けば済む話だし。
そこからの帰りに大開など歩いてみたが、このへんもすっかり改まっていて発見はなし。ふりだしに戻ってまた四番町を歩いてみたりなどし、そうして大開から電車に乗って帰った。
長田区というとどうしても震災被害を想起しないではいられない。震災の翌々日、ここに住む同級生の安否を確認し救援物資を届けるために「銀輪部隊」を結成して走った。長田区のどこであったかはもう忘れてしまったけれども、確か大開〜高速長田の大通りを通った気はする。そうして小学校に避難していた彼に会うことはできた。家は全壊全焼だったと思う。道の悲景は漠「悲惨なもの」として然とした覚えていない(。れが初めての長田区だったこともあるし。(時はポーアイとかそのへんのフェリー乗り場までしか行ったことがなかったはず)。、ともかくワケワカランことになっていてまっすぐには進めなかった。人も車も瓦礫も多く、道が道として機能していなかったしな。
あれから25年も経つのか、と思うとなんだか信じられないが、25年間ずっと見てきたわけでもなく、その後足を運んだこともないから、今日見た街並みが昔からのcontinuousな発展の結果に見えてしまったことだった。途中に大きな断絶があったことなど嘘のようである。けれども長屋街の一角に草まみれの空き地が紛れていたり、煉瓦壁の基礎だけが残っていたりもして、そんな25年分の空漠にハッとさせられたりする。震災を忘れたわけではないのである、思い出すよすがが失われていて、しかしそうやって失われなければ、新しい明日が来ない気もするのだった。