 録"
録"
nagajisの日不定記。
本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0
ad
2008-03-28 徒然 この日を編集
[ORJ] 27日-28日
昨日から鼻風邪の一歩手前とでもいうべきイヤーンな感じの体調になっている。下手に転んだら風邪引きそうな、そんな感じ。自重して地図記号描きも早めに切り上げる。というか、今回で一気に作り上げなければならんということもないような気がしてきた。他の事に注力したほうがいい。
というわけで早めに寝て、うなされて起きて、また寝て。中途半端な時間帯に目が覚めた。今日はバックエンドの仕事をちょこちょこと。頭のネジが弛んでいるから深く考えずにホイホイMLしている。
[独言] 塩田氏の事
先々日の塩田氏の件。非常に印象深い方で、これから何度もお世話になることになりそうだ。
能勢に生まれ、能勢に勤め、今でも能勢に住んでいる生粋の能勢びと。戦前から関電に勤めて、独りで北摂地域の配電関係を担当してはったという。当時は車なんて行き来できるような道じゃなかったから、自転車で、北は天王から南は伊丹の平野部まで行き来したんだそうだ。
仕事の合間に石道標を見ることが多く、それがきっかけで能勢の道しるべや古道を調べるようになった。興味は郷土史にも広がって「ダムに沈んだ〜」以外にも能勢の行事や風物などを写した写真の写真集なども作られている。
お話を伺っているといかに自分の「調査」が表層的なものであるかが思い知らされる。失われた道標や地蔵尊の行方を探してあちこち訪ね歩いたり、円山隧道の件にしても、実際に工事に携わった方に直接当たって証言を得、あいまいな記憶を検証して、それで本当の竣工年を得られている。自分みたく町史村史や看板に描かれてあることを「それしかない」と鵜呑みにするようなことはない。真に郷土史家というべき人だと思う。
伺った日の帰り、またカイモリ峠のそばを通ったのだが、前回訪れた時に見つけられなかった道標の一部が別の場所にあるのを発見した。塩田氏からいただいた「能勢の街道」の冊子にも亡失とある。今日電話してお伝えしたら大層喜んでいただけた。自分も単純に嬉しい。
・・・稲荷坂のアレは、レアじゃなかったけどorz。あっはっは、勉強が足りないぜ!
2012-03-28 この日を編集
[企画] Tシャツ届いた&発送した
ヘビーウェイトモスグリーンLと化繊ブラックMが余る予定なので,ご希望の方は連絡ください.
今回のTシャツは球磨三郎さんのクレームを受けて隧道口の高さを合わせている.ぴったりでないのは柱本口が若干埋もれているのでということで.このデザイン修正で版下代が発生したとかいう勝手な事情は口が裂けても言えない.
[独言] 今日は仕事したぞ
旧町村名を現行市町村に振り分けるプログラムを書いて工場通覧をフィルターした.久しぶりに書いたら二次元配列の書き方忘れてたり.=の使い方が間違ってたりして壺.しかし一番時間を食ったのは篩に残ったのを手作業で振り分けることだったり.元データからして間違っとるんや!
鉱山一覧はすでに分けていたので上記にimplode.特と登をマージして要約するのにまた時間を取られた.
[料理] ソース焼き飯
芽の出たスカスカな人参を刻んて炒めて中華スープの素を少々加えてご飯を放り込んだものにオタフクのお好み焼きソースをかけて炒めたところ存外に旨いたべものができた.調子に乗って第二陣を作っている.今度は芽を刻んで入れてみよう.
タンパク質?なにそれ食べられるの?ああ,鮭フレーク一匙入れたっけか.
2013-03-28 この日を編集
[近遺調] 奈良県指定府県道
T15とS11の比較を完成させた。すっきりした!
指定府県道になったことで内務省の監督を受けることになったということは、指定府県道路線の道路・橋梁の改修は道路規格が守られたのだろうか? 端駆橋、磐余橋あたりは比較的広い。横田の鋼桁橋も。八尾大橋は若干狭しか。
府県にとってはあまり利点のなかった制度。かえって指定が足枷になったようにも読める。奈良県の場合、指定府県道に相当する路線は古いまま現在に至っているところが多い。橋が若干広いかなという程度で、東熊野街道沿いのはやっぱり4.5m強。市街地なんかは特に狭いままなのが多い(新八号とか上街道筋とか)。
若干スレチなメモ。奈良県は大正10年と昭和2年に県道大改修を企図。特に後者は当時116里あった2間幅の県道を4間幅に拡幅しようというもの in 15ヶ年計画で、工費は起債で賄うことになっていた by 奈良県議会史第2巻。S12以降鋼材不足で起債工事を全ストップしたという話はモロにこれにひっかかってくる。 あと県道橋梁は鉄橋のほかは土橋にすべしっていう建議があったな大正時代に。
県議会史はとても参考になるが、決定された後のことがあまり出てこないのが苦しい(具体的にいつどの道を改修したか?とか、どこまで改修が進んだのか?とか)。出てきても繰延とか支出割変更とかいったマイナスの話題ばかりだ。
[道路元標][道路遺産] 奈良県里程元標跡
 明治里程元標のほうはちゃんと解説看板が設置され、復元前の位置にプレートがはめ込まれていたりするのだが、その隣に設置された道路元標はまるでオマケの扱いだ。余りに哀れだ。そんなんだからどんどん失われてくんだ!ベサツだベサツ!と憤ったりしたけれども、憤ったところで何になるわけでもなし、憤るようになったのもつい最近のことだし。俺のものでもないしなあ。
明治里程元標のほうはちゃんと解説看板が設置され、復元前の位置にプレートがはめ込まれていたりするのだが、その隣に設置された道路元標はまるでオマケの扱いだ。余りに哀れだ。そんなんだからどんどん失われてくんだ!ベサツだベサツ!と憤ったりしたけれども、憤ったところで何になるわけでもなし、憤るようになったのもつい最近のことだし。俺のものでもないしなあ。
結局のところ、それが観光資源になり金づるになる(と踏んだ)から持ち上げるのだ。役に立つから注目するのだ。注目されないものは忘れられて行くのみで、まるで自分みたいだと思う。後で惜しまれることもないに違いない。
今朝生駒市の教育委員会さんから電話をいただいた。行方不明になっていた南生駒元標かも?というTELだったが、どうも違うもののよう。まさか元標に右宝山寺と刻んでたりはしないだろう(「尋ねて」の写真では表面が露出した状態しか写ってないからその側面に追刻されてたら知らない)。 自分が若干寝ぼけ気味で失礼をばしたかも知れぬが、しかし続けて探して下さるとのことで頼もしく感じた。今から数十年前の話だというのにしっかり追いかけて下さっていることに対し、無上の感謝を申し上げたく思う。県の職員がみな×××だと思っているような人とはお知り合いになりたくない。
短い電話の中で教育委員会さんがそういう道標を回収していた過去があるらしいことを教わった。まあそれが第一候補ではあるだろう。
[竹筋] 大阪府府県道三島江茨木線第11号床板橋

 原文にあたって納得した。作った本人が言うからには竹筋に違いないと思う。 橋長3080mm、厚340mmということは側面から見える厚さがそのくらいになるはずで、 2008年の正月早々橋の下に潜って確認した番線の入った板桁はさらに一段下がっていた(写真セレクト不味いな…)。そこまで含めると34cmをはるかに越えてしまう。追築されたものであったらしい。
原文にあたって納得した。作った本人が言うからには竹筋に違いないと思う。 橋長3080mm、厚340mmということは側面から見える厚さがそのくらいになるはずで、 2008年の正月早々橋の下に潜って確認した番線の入った板桁はさらに一段下がっていた(写真セレクト不味いな…)。そこまで含めると34cmをはるかに越えてしまう。追築されたものであったらしい。
原文は1985年の「セメントコンクリート」に収録。撮ってきた写真をよく見ると、 鉄筋桁とその上の板桁との間に 「(茨)木市水( 道局) 」「1988」とプリントされたパイプらしきものが埋まっているのが写っていた。原文後に手が加えられたものらしく、それで今でも持っているのかも知れない。
2023-12-01追記:日本橋梁協会『虹橋』第34号に掲載あり。これはフリーに見れる。 https://www.jasbc.or.jp/technique/nijihashiback/files/nijihashi34.pdf
2014-03-28 この日を編集
[KINIAS] 見学会@三木市

の簡易報告を25日の晩に書いたつもりだったのにプレビューしただけで消したようだ。不抜けめ>nagajis。バツとしてアサリ起こし三千歯。終わったら左下の隠しカメラに向かって尻振り百回な。
[煉瓦刻印][煉瓦] 貞徳舎耐火煉瓦「TTR」

常三郎さんとこで。明治20年代から大阪で耐火物を作り続けているこの会社の耐火煉瓦を、会社の工場前の縁石以外で見たことは、実はない。
三木市街をじっくり歩いて回る時間がなく、管見では古い赤煉瓦を見つけられなかった。鍛冶屋の多い街だから耐火物の古物はたくさんあるかも知れない。現に常三郎さんのところにはマーク入りのOYKなどが転がっていた。そういう場面で見つかると流通を跡づけられていいのだが、インテリアやガーデニングの素材としてヤフオクされているご時世だから、たいていは同定に使えない。ちょうど、人の移動が昔よりも自由にかつ頻繁になって、苗字で出身地を言い当てることができなくなったのと似ている。
[道路元標] 久留美村道路元標

移動中のバスの中から見つけた。あると知らずに見つけたものほど嬉しいのはなぜだろう。自分が知らなかっただけで、自分が生まれるはるか前からそこに在ったものなのに。
廃道や遺構も同じ。自分が第一発見者なんてことはあり得ない。誰も知らない廃道なんて存在せず、あるのはただ己の慢心と顕示欲だけだ。ということを前提に書くと廃道ルポはかなり難しい修行になる。誰にもおすすめしない。
[奇妙なポテンシャル] #334
 最後に立ち寄った道の駅三木で。アスファルト舗装のロードローラー。会社のマークを見て
最後に立ち寄った道の駅三木で。アスファルト舗装のロードローラー。会社のマークを見て
新和窯業と吉名煉瓦の組み合わせだ
と思って独り興奮した。
ワケワカメを投げつけておいて一旦中断。
[煉瓦刻印] 吉名煉瓦@豊中市曽根
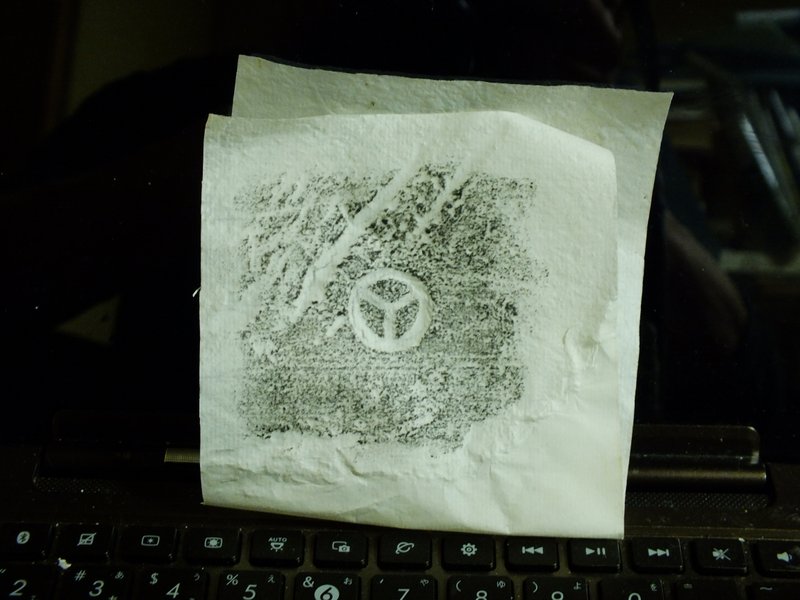
吉名煉瓦の刻印の拓本。つい先日帰りがけに採取した。空き地に猫がいたので近寄っていったら雨に洗われて露出していた。猫そっちのけで掘り返した。
YoshinaのYを○で囲ったもの。一本足すとピースマークになる。ということはどうでもよく、広島の煉瓦がここまで及んでいることに驚きを禁じ得なかった。とはいえすでに山陽煉瓦のSRKは見つかっている>岡町。大阪でもここまで広域の煉瓦が集まっているところは少ないはずだ。だんだんこの街の特異性がわかってきた。どういう流通機構があってこうなったのか知りたいものだ。
[奇妙なポテンシャル] #334(続)
んでロードローラーの話である。新和窯業は○にSである。○にYの吉名煉瓦を足せばこのマークになる。それに気づいたことに奇妙なポテンシャルを感じたのである。もうちょっと正確にいうとそれに気づいたnagajisの神経にである。その気づきを記録するためだけにこの写真を撮ったことにである。
おそらく世間一般では「俺ってスゲー」か「俺って異端」と続けるところだろう。新和窯業の刻印が○にSだと知ったうえで吉名煉瓦のことも識り○Yだと知ったうえ重ねてみるという発想がなければ出て来ない気づきだ。偉業か阿呆業かのどちらかだろう。しかしあいにく私は一般以下なので同じ轍を踏まない。誰にも伝わらない発見をし独りで悦に浸っているnagajisを哀れに思っただけだ。
続いて思ったのは
あれ、そうすると○が重なるんじゃね? 打ち消されてS+Yになるんじゃね?
であった。さらには
いやいや、SとYの重なったところも消えるんじゃね?
とも思った。誰がXORを取れといった>nagajis。
結論はない。強いて言えば「煉瓦刻印を知っていると暇つぶしができる」ということくらい。
[奇妙なポテンシャル] #335
そのうえ吉名煉瓦の採取地を見失った。それまで数度その前を通っていた空き地だったのだが、採取後にもう一度行こうとして、これまで3度失敗している。古いクリーニング屋のある辻を南に行った所だったようにも思うがそのクリーニング屋の場所からして定かに覚えていない。もっと171寄りのような気もする。あまり行き過ぎると豊島煉瓦予定地のあたりになる、あの辺り。帰りに二宮金次郎の交差点の信号操作函の上に置いたのは覚えているから、そこから南下したところであるはずだ。
そういや豊中には大和煉瓦もあったんだよな。庄内のほうだけど。これで江州煉瓦の○Gとか和歌山の分銅形とか見つかれば最強。
[げ] かく
くだらねえことはいくらでも書けるなあ。楽だなあ。それに引き換え、といういつもの感想。そして探索中に思ったことを書くと妙に説教臭くなるのはどうしてか。根が坊主だからか。隠れ坊主。響きだけはいいな。
前編で背景を説明し切ったので楽っちゃあ楽。
2016-03-28 この日を編集
[雑] 木管・くずし字解読システム
http://mojizo.nabunken.go.jp/index.php
結構有り難い。これでアジ歴のくずし字読める!と思ったけれど防禦造営物の「禦」は読んでくれんかった。ま、ヒントが貰えるだけでも便利だし、前後脈絡で読まないといけないのは従前だ。
[煉瓦刻印] 貝塚煉瓦?@五條市街

形状は貝塚煉瓦なのだけれども発見場所がまずい。前掲H★M刻印の隣に転石っていた。五條市街の駅近くの通りに面した花壇。
(1)岩橋煉瓦の井桁を斜めに押した可能性
見た感じでは菱井桁っぽかったけれどもな。写真の角度では正体でもひしゃげて見えよう。
(2)(推)吉野煉瓦のバリエーションの可能性
大淀くんだりから流れてきたものかも知れぬ。今のところ太い菱井桁しか見ていないけれども細いのがなかったという保証はない。
なにより引っかかるのはブツが貝塚煉瓦っぽくない気がするところ。ちょっと寸詰まりじゃなかろうか。あと貝塚の刻印は細くて鋭いのが多い。こんな感じの鈍らった線じゃない気がする。そうして貝塚煉瓦はこんなど真ん中に押さない。
でもまあ五條だからなあ。紀和鉄道と南和鉄道の接点だからなあ。貝塚でも間違いじゃないんだろうけどなあ。
と、いかにも通ぶって悩んでいるnagajis哀れ。これが貝塚煉瓦だったとしても岩橋煉瓦だったとしても吉野煉瓦だったとしても世界はこれっぽっちも明るくならない。
2022-03-28 この日を編集
[奇妙なポテンシャル] ワラタ
転落(ババババベラガガラババボンプティドッヒャンプティゴゴロゴロゲギカミナロンコンサンダダンダダウォールルガガイッテヘヘヘトールトルルトロンブロンピピッカズゼゾンンドドーッフダフラフクオオヤジジグシャッーン!)
に衝撃を受けた。原文は"The fall (bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonner ronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk!) ".
2025-03-28 この日を編集
[煉瓦] 『滋賀県史研究』届く
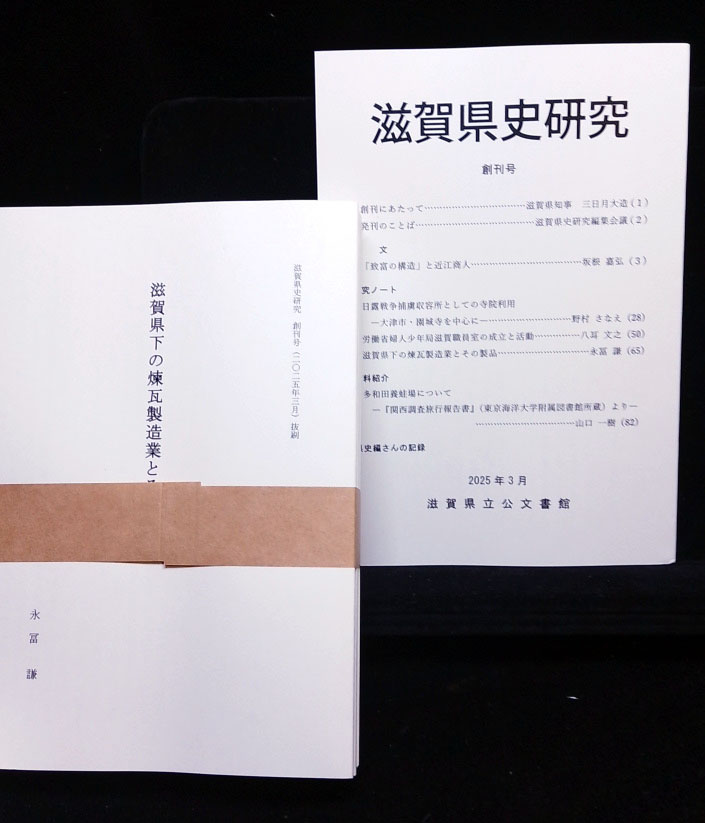
ああ、疲れた。そして非常に居心地が悪い。
抜き刷りを20部も下さったが配る相手がいない。読んでやってもよいという方は送料無料で差し上げますんでnagajis@the-orj.orgあたりにご連絡ください。

_ とと [春ですなぁ…ほんま。]
_ Bee [確かに春だわ。寒いけど・・・。]